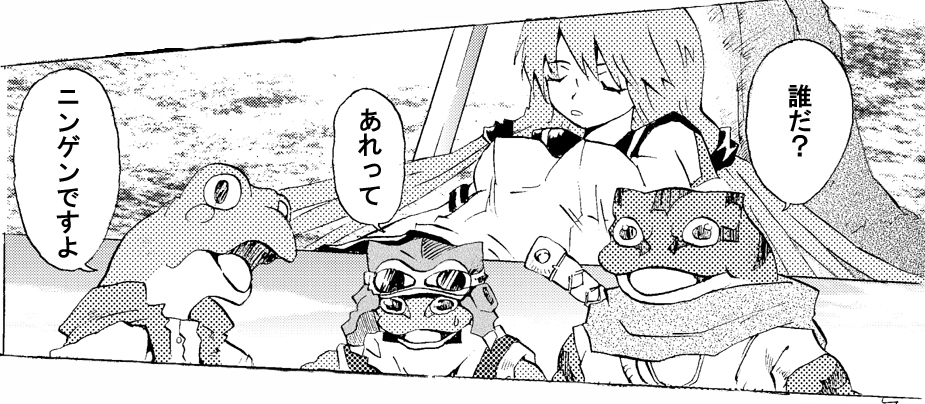
汗が張り付く不快感と、ゲコゲコ五月蠅い鳴き声で、少女は重たいまぶたをゆっくりと開けた。
最初に違和感を覚えたのは、砕けた石の破片が散乱する地面で自分が寝ていたことだった。
あれ? どうしてだろう?
なんで私、地面で寝ていたんだろう?
視界に自分の履いたローファーと、少し土で汚れてしまった制服のスカートが映る。
ここ、どこ?
家じゃない……。
まるで、山の中にいるみたい。
それにさっきからゲコゲコとカエルかな、鳴き声が聞こえる。
都会で暮らす自分には想像もつかなかった。
田舎の山の中がこんなにも騒々しいなんて。
待って。なんで田舎にいるの?
私寝る前なにしてたんだっけ?
たしか、学校から帰宅途中だったような……それで神社の境内で……光に包まれて……。
とにかく身を起こそうと顔を上げた瞬間だった。
「ひゃあぁぁぁッッッ」
考えるより先に悲鳴を上げてしまった。
無理もない。
意識が朦朧としていた自分を囲むようにして、不思議な生物がゲコゲコと喚き散らしていたのだから。
カ、カエル?
それはあえて近い生物を挙げるならばカエルだった。
小学生ぐらい大きなカエル。
服も着てる。
帽子もかぶってる。
あ、一匹だけクツまで履いてる。
カエル?
カエル人間?
さ、三匹もいる……。
突然の少し高い声で発せられた悲鳴に、三匹は喧々諤々とした意見交換を中断した。
腕組みをして唸っていたウシツノがその様子を見て口を開く。
「おい、そのニンゲン? 怯えているんじゃないのか? いまの悲鳴に聞こえたぞ」
アマンが信じられないといった顔をする。
「まさか! ウシツノの旦那は知らないようだが、そもそもニンゲンというのは強欲で、その上ずる賢く、他種族に対して常に威張り散らすような奴らなんだぞ。吟遊詩人がそう歌っていたからな。マラガで聴いたんだ」
「それは偏見が過ぎますよ。それよりまずは彼女に事情を聴くべきでしょう。まさかこんなことになるなんて」
アカメの感想はアマンもウシツノも同意見だった。
三匹とも白光現象の調査に来ただけだった。
何もないと高をくくっていた。
それがまさか、この地では珍しい種族、ほぼ目にする機会のないニンゲンが、それもなんとも美しい白い剣と共に眠っていたのである。
なんとなくだが、すでにそれぞれの胸には畏敬の念が生じていた。
「さて、そうはいってもまずどうしたものか」
長老の息子として、まずは自分が率先せねば、とウシツノが思案を巡らせるていると、機先を制してアマンがニンゲンに話しかけていた。
「おい。お前ニンゲンだろ? ここでなにしてるんだ?」
好奇心を抑えられなかったが、それでも用心のため腰のだんびらに指は掛けている。
「……」
しばらく返答を待ってみるが少女からの返事は来ない。
目をぱちくりさせるだけで、声すら出てこない。
「お、おい、聞いてんだろ? 答えろよ」
「だめですよアマンさん。我々の言葉で話しても。せめて西方語をお使いなさい」
「あ、ああそうか」
カエル族にはフロッ語という独自の種族言語がある。
それはカエル族だけではない。
この世界に住まうすべての知的種族には、それぞれの種族言語が存在する。
しかし当然だが、他種族との意思伝達にはより利便性の高い公用語も存在する。
ある程度の知性がある者ならば、それらを当然のように駆使する。
この地域で広く使われているのは西方語だ。
世界に二つある大きな大陸のひとつ、ここ西の辺境大陸で最も通用する言葉である。
いかに辺境のカザロ村といえども、外部との交流が全くないわけではない。
そこで彼らも一般教養としてこの西方語は修めている。
まあ多少のカエル訛りは仕方ないところだが。
「よ、よし。いくぞ」
アマンは改めて少女に問いただした。







